インターフェロンとがん①
インターフェロンは1954年に東京大学伝染病研究所に所属していた長野泰一と小島保彦により発見・報告された。両名はウサギの皮内に天然痘不活化ウイルスを接種する実験結果からウイルス感染組織内には、干渉能のあるウイルス粒子、ウイルス抗原、抗ウイルス抗体とは別に、ウイルス感染を抑制する液性成分が含まれていると結論し、その成分をウイルス抑制因子(inhibitory factor)と名付けた。
1957年に別のグループであるA. IsaacsとJ. Lindenman (National Institue of Medical Research)が、ニワトリの胚に熱不活化処理したインフルエンザウイルスを投与させると、細胞から産生されるタンパク質がその場所でほかのウイルスの増殖を抑制することを見出し、ウイルス干渉(viral interference)を誘導するそのタンパク質をIFNsと名付けた。日本国外では、この1957年の報告を最初の発見としていることが多い。
(上記2報は下記リンク先より確認できる。)
http://www.pharm.kyoto-u.ac.jp/bisei/NaganoKojima.html
当時は、ウイルス感染や悪性腫瘍にも効くともてはやされたと長野先生の著書「インターフェロンとは何か」にも記載されている。

ちなみに、1980年のTIMEでも特集され表紙を飾っているようだ。
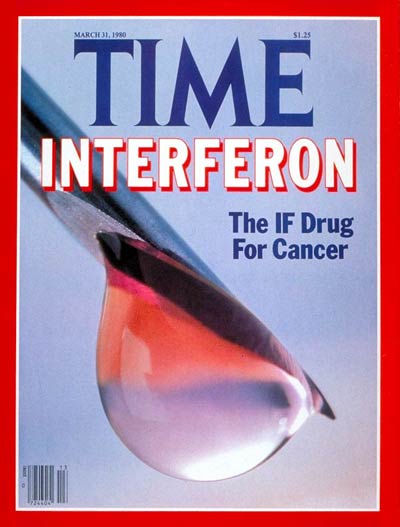
「インターフェロンとは何か」は下記のまえがきから始まる。
よい基礎医学者は強靭な観察力と透徹した論理を持っているが、胸の奥底には病む人の苦しみ、悲しみ、死の恐怖を、ともに苦しみ、怖れる心を持っている。
その温かい心は信仰に根ざしている場合もあり、倫理に支えられている場合もあるだろうが、ごくありきたりの人情にほかならないことの方が多い。日本の中世の唄に、
ただ人は
情あれ
あさがおの
花の上なる
露の世に
というのがあるが、これはわれわれ日本人にとってはごく自然な思いである。この柔和な心情と、鋼鉄のような実証精神とが結びついて、医学の研究は営まれている。
研究者自身は、試験管や実験用動物に囲まれて研究に没頭しているのは専ら生物学的あるいは物理化学的興味に駆り立てられてのことだと日常思っているが、心の底には病む人への思いが沈んでいる。自ら意識しないだけである。
医学の進歩は、このような思いをもった幾多の研究者たちの努力の上になりたっていることを深く感じさせる一文である。